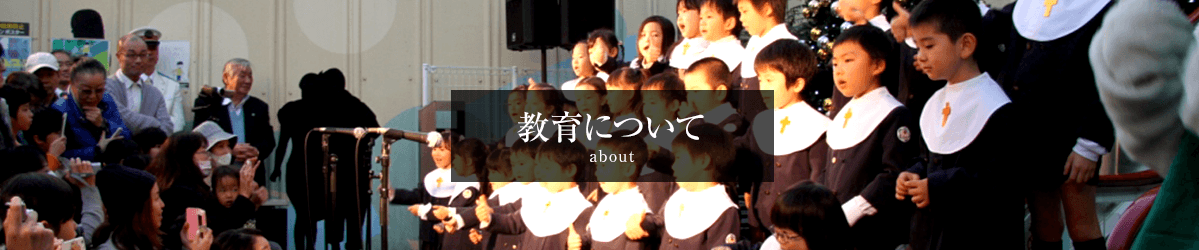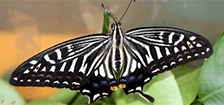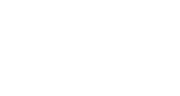スローライフ
「子どもができたら、田舎に帰って自然の中で育てたい」
そんな風に思ったことはないですか?
文明がどんなに発展しても、子どもが育つプロセスは何も変わっていません。感覚が育ち、遊ぶ力が育ち、身体が育ち、考える力が育つ。身の回りに直接感覚を味わうことができる刺激があり、自由に遊び身体を動かすことができる環境があり、自分で考え試行錯誤する時間と空間がある。その中で、子どもは自らのこころと身体を使って育っていきます。
ところが、現代の都市部の子育て環境には、そのいずれもがありません。そのことで、子どもたちの育ちに様々な偏りやゆがみが生じてしまっています。多くの人々は、そのことを感覚的に察知し、「子どもを育てるなら田舎で…」と考えます。しかし、実際にそれをかなえるのは現実的になかなか難しいことでしょう。
双葉幼稚園にはそれがあります。季節ごとに様々な花を摘み、野の鳥の声を聴き、実りを味わいます。風に身をゆだね、土のにおいを嗅ぎ、芝生を駆け抜けます。
徹底したスローライフがそこにはあるのです。
そんな、一見ゆったりした生活の中で、子どもたちの五感は研ぎ澄まされ、こころも身体も育っていきます。ここで過ごす時間は、子どもたちへの最高のプレゼントだと思います。
自然の中で育てるということ
双葉幼稚園の園庭は、23区内とは思えないほど自然が豊かです。その理由は、子どもたちには自然の中でその恵みを与かりながら育ってほしいと願っているからです。
双葉幼稚園の春は、梅が咲き、桜のつぼみが膨らむところから始まります。園内の田んぼではヒキガエルが卵を産み、野の草が芽を出し始めます。4月に新しい園児たちを迎え、彼らが元気に遊び始める頃には、園庭は色とりどりの野の草花が咲き乱れ、子どもたちはさっそく花束を作り、ままごとの飾りつけに使って遊ぶようになります。そして5月には、年長児が園内の田んぼで田植えを行うのです。
夏が近づくと、草木や果樹が実をつけ始めます。キイチゴ、ウメ、ビワ、クワ、モモ…。子どもたちは自分で収穫し、みんなでそれをいただきます。園内の畑では、ジャガイモを収穫。木々の上では、今年生まれたムクドリの雛たちが親に連れられて飛ぶ練習に励み、子どもたちは木の下で応援します。
こんな生活を送っていると、子どもたちの中に大切なものがいろいろ育ってきます。自然の恵みをいただくことへの感謝の気持ちや、限られたものをみんなでわけ合おうとする気持ち、小さなものへの優しさ…。もちろん、知的好奇心や探究心も。
このようなこころは、昔は自然に育っていたはずですが、今は幼稚園や学校などで意図的に経験できる環境を作らなければ育たない時代になってしまいました。だからこそ、失うわけにはいかないと思いませんか。わたしたちはそういう思いで、樹を植え、畑を耕しています。
絵本との出会い
子どもは絵本が大好きです。お気に入りの絵本を何度も持ってきて「読んで」と言います。内容を知っていて文章を覚えるほどになってもやっぱり持ってきます。それは大人から見るとちょっと不思議なことかもしれません。子どもにとって絵本はそれほどに大切なものなのです。
子どもも大人も、絵本を読むとこころが動きます。登場人物に感情移入して、嬉しくなったり悲しくなったり。また知らなかったことに触れてワクワクしたりもします。子どもは絵本を読んでもらっていて嬉しくなったり悲しくなったりした時、「読んでくれている人も同じように嬉しくなったり悲しくなったりしている」と考えます。もしかすると、読んでいる大人は別にこころが動いていないかもしれませんが、子どもはそうは思っていません。読んでいる大人と読んでもらっている自分が同じ空間で、同じ気持ちを味わっていると感じています。そしてそのことに、この上ない安心感・満足感を抱いています。
子どもにとって絵本は、大好きな人と同じ時間と空間を共有し、同じ気持ちを感じる機会でもあります。だから、いつも同じ絵本でいいのです。かえってその方が安心なのです。その安心感があって、いつでもその時間に戻れるという確信があって、初めて子どもたちは外の世界に一歩踏み出すことができます。それは、他の分野の絵本だったり、新しい遊びだったり。だからまずは、子どもたちの絵本への思いを、しっかり受けとめてあげたいですね。
ご家庭と園とのコミュニケーション
双葉幼稚園では、ご家庭と園のコミュニケーションを大切にしています。それは、お子さまの健やかな育ちを支えるためには、ご家庭と園とが同じ気持ちで情報を共有しながら保育を進めることが必要不可欠と考えているからです。送迎時は担任が直接お預かりし、帰宅時はその日の様子などをお伝えした上でお子さまを引き渡します。
また個別面談を学期ごとに年3回行っており、必要に応じて別途お話しする機会も設けています。お子さまのお誕生日には、1日保育体験の機会も設けており、お子さまの園での様子や当園の保育体制などをじっくり見ていただくことが可能です。その他、保護者参加行事などが多数あり、保護者の皆さまと園とがいっしょに子どもたちを育てるという体制作りに努めています。
ご家庭と園が、それぞれどんなに子どもの育ちに良いことをしたとしても、考えや方針がバラバラでは子どもが混乱してしまうだけです。子どもたちの育ちがより豊かなものになるように、ご家庭と園とが手を携えて歩んでいくことができたら素敵ですね。


今の子どもたちは、祝福されているでしょうか。
いじめに遭ったり、受験競争に追われていたり、
ストレスを溜めて自分を失ってしまったりしていないでしょうか。
子どもは祝福されるべきもの。そして一人ひとりが、備えられた賜物を使っていきいきと生きていけるよう、育って欲しい。双葉幼稚園は、そのような人生で一番大切なところをしっかりと見つめ、
子どもたちを育てていきたいと願っています。
子どもたちが、神さまに祝福されて生きていくことができるように、そして神さまと人々に愛される人になるように育てます。

・子ども一人ひとりの思いを受けとめ、その子らしさが十分に発揮されるように育てます。
・愛されることで愛することを知り、信頼されることで人を信頼することのできる人に育てます。




本園は、建学当初からキリスト教精神に基づいた教育を行っております。
キリスト教だけではないですが、宗教を信じている人とそうでない人の違いは、自分が今生きていることを、生かされていると考えるか、自分の力で生きていると考えるかの違いに表れます。
生かされていると考えている人は、生きていることに感謝の気持ちを持ちますし、様々な人との出会いも感謝の気持ちを持って受けとめます。
また、何らかの苦難にぶつかった時にも、それにより自分に与えられたことの意味を考え、それを乗り越えることに人生の意味を見出そうとします。
すると、どうして自分だけがこんな目に遭うのだと自暴自棄になったりしませんし、苦難から逃げ出したりもしません。
自分が生かされていると考えるところから、どんなことにも感謝の気持ちを持ち、物事に常に前向きな気持ちで取り組めるようになるのです。
わたしたちは、子どもたちにもそのように生きていって欲しいと願っています。
これは、キリスト教、仏教、神道などあらゆる宗教を超えて、すべての人が根源的に願っていることだと思います。
しかし、人は暫しそのことを忘れ、目先のことで一喜一憂しがちです。
そんな自分たちの在り方をもゆったりとした目で見つめ、子どもたちを包みこんで育てていきたい。双葉幼稚園は創立時からずっとそのように願っています。

2013年度より、第5代園長の重責を担うことになりました。
江戸川双葉幼稚園は、1941年11月29日に創立されました。日中戦争のさなか、そして太平洋戦争前夜という大変な時期であり、子どものことなど世の人々がかまっていられない時期でありました。そんな中であっても、子どもたちがのびのび遊ぶことができる場を提供したい、そしてイエスキリストの愛の精神をもって子どもたちを育てたいという初代園長・牧師の願いから、この幼稚園は始まりました。
その日からすでに70年余の月日が経ち、時代は大きく様変わりしました。双葉幼稚園も、時代の変化に応じて変わっていかなければなりません。皆さまにご指導いただきながら、変えるべきところ、変えてはならないところを吟味しつつ、子どもたちを育てていきたいと考えております。
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。2017年5月
園長 菅原 創


歴史
1941年(昭和16年)に江戸川区で初めて認可幼稚園として創立。
1987年(昭和62年)よりキリスト教会付属幼稚園から学校法人菅原学園 江戸川双葉幼稚園に。
2022年より幼稚園型認定こども園へ移行。


幼児教育の役割について、改めて考えてみたいと思います。
幼児教育の世界では以下のような力を育てたいという方針のもと、日々教育活動に取り組んでいます。1. 母親から離れても情緒が安定し、自己を発揮できる力
2. 自分のやりたいこと、やるべきことを自分で見つける力
3. 自分で考えて行動する力
4. 友達の気持ちや立場を理解し関係を作る力
実際には他にもたくさんあるわけですが、主なものだけを挙げてみました。では、現場ではどのようにしてそれらの力を育てているかをご説明します。
(1)母子の分離場面が無理なく行われるように、子どもの気持ちを受けとめ、時間をかけて保育者との間に良好な関係を作ります。
(2)自由に遊び探索できる環境を、発達状況に合わせて作り、援助します。
(3)遊び方が決まっていない遊具や素材を発達に応じて用意し、結果が出るまで見守り援助します。
(4)多人数で取り組む遊びの環境を用意し、けんかやトラブルの場面でも友達の気持ちや考えに気づくことで、友達関係が充実していくように促します。

幼児教育は人生の基礎工事
上記の内容は、子どもたちが将来生きていく上で大切な事柄ばかりです。つまり、幼稚園というところは、人生の基礎工事をするところなのです。どんな建物を建てるにも、基礎工事が最も大切です。それは人生においても同じです。
建築の基礎工事では、コンクリート厚をどれぐらいにするか、鉄筋の張り方と本数、コンクリートを流す回数と手順など、様々なことを考慮しなければなりません。職人は誰も知らないところで知識や技術を着実に磨き、仕事に取り組んでいます。
基礎がなければ工期も短く費用も安くなりますが、後々大変なことになってしまいます。教育も同じです。人生の基礎工事においても、それを行うための知識や技術があり、その基本的な部分は大学で学びます。教員たちは日々それを磨き、地味で目立たない作業を積み重ねていくのです。
もちろん基礎よりも、英語や逆立ちや勉強や習い事など、結果が目立つ事柄に力を入れることもできます。しかし、それでは基礎工事がおろそかになってしまいます。
基礎がおろそかにされていませんか?
最近、児童・生徒や若者たちの姿を見ていると、幼稚園で育っているべき人生の基礎の部分が育っていないと感じることがよくあります。
例えば、ネットやSNSに精神的に依存し、勉強が手につかなくなっている生徒。成績は良いのに、自分で考えて行動することができず、指示待ちになってしまう新人社員。言われた仕事はきちんとこなせるのに、企画書を作らせるとさっぱりできない人。自分の専門分野については人並み以上の知識と技術を持っているのに、人の気持ちや立場を考えることができない人。
みんな、幼稚園で育つべきものが育たずにきてしまった例です。このような力は、小学校以上では育てるための科目もプログラムもありません。そして、その力が育っていないのは、その人自身の問題と思われてしまっています。しかし、そうではありません。その人が通っていた幼稚園の問題です。
母親に依存した乳児期からの第一歩がしっかりしたものであれば、情緒はいつでも安定し、ネットもSNSも依存することはなく便利に使うだけです。自分で考えて行動する力が育っていれば、指示待ちにはなりません。自分がやりたいこと・やるべきことを自分で見つける力が育っていれば、企画書は次々出てきます。人の気持ちや立場を考える力が育っていれば、知識や技術はもっと活かされるはずです。
基礎工事をおろそかにすると、どんなに成績が良くても、それをその人の人生に活かすことはできなくなります。
その子らしさが活かされる生き方
人は誰でも、神さまから与えられた性格や能力があり、それを活かして生きていくことが、その人らしさが最も発揮され、周りの人々にも喜ばれることにつながります。そして、幼稚園は、それらがしっかりと伸びていくための基礎の部分を作る役割を担っているのです。
世間には、その人にはない能力を小さい頃から身につけさせようとする風潮があります。そして、ともすると「その人らしさを発揮できずに生きる人」を作り出してしまうおそれもあるのです。
幼稚園では、一人ひとりの基礎の部分をしっかり育て、その子に与えられた能力が伸びていくための土壌を作りたいと思っています。またそういう思いを、ご家庭の皆さまとも共有していくことができればと願っています。園の特色